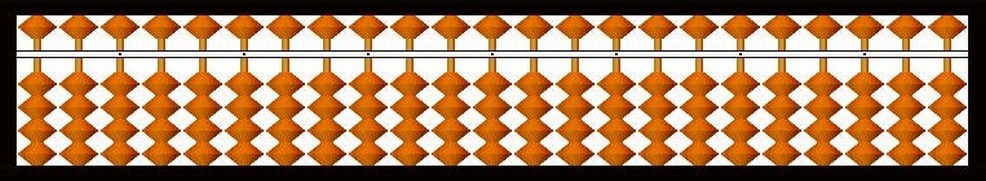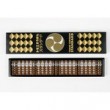親が知っておきたい子供が直面するそろばんの壁

子供に習い事をさせている親であればそろばんに限らず、どんな習い事でも壁に直面します。
そろばんの授業に対して気が乗らなかったり、辞めたくなることもあるでしょう。
それをなだめ、励まし、モチベーションを上げて習い事を継続させるのも親の役目の一つですよね!
しかし、もし親御さんがそろばんに精通していなかったら、子供がどんな壁に直面して悩んでるのか理解するのはなかなか難しいですよね…。
もちろんそろばんの先生に相談する人もいるでしょう。
しかしそろばんの先生の中には「そんなのみんな同じですから大丈夫ですよ~。」のなんとも頼りない一言で終わってしまうかもしれません。
確かに教える側であれば、みんな同じ壁に直面し、いずれは乗り越えていくのを見ているので、あまり深刻に捉えません。
でも親御さんにとっては、なんとも不安ですよね…。
そこで今回はそろばんを習う子供が直面するそろばんの壁について簡単に紹介します。
※級については日珠連や全珠学連が基準になります。
そろばんの壁
10級の壁(知識の使い分け)
そろばんを習い始めて、指の動かし方や数の表し方を学んだ後に、習うのが4つの基礎となる計算です。
私の解説では「5をつくる」「5から引く」「10をつくる」「10から引く」と表現しています。
この4つの使い分けが1つ目の壁になります。
特に同じ足し算の「5をつくる」と「10をつくる」、引き算の「5から引く」「10から引く」のどちらを利用するのか理解しなければいけません。
また、指の動きだけでなんとなくこんな感じだったよな~で進んでしまうと、足し算なのに引いてしまったり、その逆をすることがあります。
しっかりと理解をすることが必要です。
ここがすっと頭に入るかどうかは個人差があります。
悩んでいる場合は急がずに時間をかけて、同じ問題で練習しましょう。
少しでも穴がある状態で先に進んでしまうと、結局後で見取り算で苦労することになります。
九九の壁(2年生の夏まで)
足し算引き算を乗り越えると次は掛け算を習います。
掛け算を出来るようになるには当然ながら九九を覚える必要があります。
小学校では2年生の秋以降に九九を習うので、それまでに掛け算を習う子は九九を覚えなければいけません。
もちろんそろばん教室で全部覚えてから先に進むのが理想ですが、現実はそんな簡単に覚えることはできません。
それに九九を暗記するのに時間を掛けすぎるわけにもいきません。
よって多くのそろばん教室では初めは九九表を見ながら解いてると思います。
しかし九九は本当に大事です。
4年生、5年生になっても怪しい子はいます。
特に6,7、8の段で苦労します。
九九だけはみっちりお家で頑張ってもらいたいと思っている指導者がほとんどだと思います。
6級の壁(割る数が2桁の計算)
7級までスムーズに進級出来た子でも、6級で壁にぶつかる子は多くいます。
その理由が割り算の割る数が1桁から2桁になるからです。
割る数が2桁になると、新しく習う知識がいくつか出てきます。
より詳しい内容については別途、そろばんの6級の壁にて紹介しています。
5級の壁(大還元の使い分け)
5級も6級同様に割り算になります。
6級では割る数が2桁に対して、5級では3桁になります。
それに伴い6級で習った戻し算(小還元)に加えて、新たに大還元という戻し算の知識を学びます。
この2つの使い分けで混乱してしまうことが多くあります。
とは言っても小還元でも、大還元なんて親御さんにはわからないと思うので、ここはそろばんの先生に任せましょう。
また、5級ぐらいからある程度の計算スピードが必要になります。
自宅で練習するなら、掛け算と見取り算を時間を計って練習するといいと思います。
4級の壁(計算スピード)
5級を合格すると、次の4級では新しく習う知識はほとんどありません。
5級の延長線にあるのが4級です。
掛け算、割り算、見取り算ともに5級から1桁増えるので、それに伴い計算スピードが必要になります。
プリント演習をすると、計算も出来る、答えも合う、だけど解ける問題数が少ないという状態になると思います。
ここは上級者へと続く階段の1段目になります。
上級者と同じ無駄のない解き方や、計算感覚を指導されつつ、練習しましょう!
この壁を突破するには、根性論ではありませんが、時間を計ってプリント演習をこなす必要があります。
2級の壁(計算スピード)
4級を突破すると、小数や四捨五入といった知識を学びます。
全珠学連の3級からは伝票を習います。
準2級では補数計算(見取り算のマイナス計算)を習います。
しかしこのあたりは壁というほど難しいことはなく、どの生徒も理解はします。
そして3級、準2級までは検定試験も比較的スムーズに合格するケースは多く見られます。
しかし2級ぐらいからまた壁が現れます。
それが計算スピードです。
3級以上になると進級するごとに1桁増えます。
よってその分計算スピードが必要になります。
4級からさらにもう一段上の速さが求められるのです。
ここを打開するには4級同様に、プリント演習をこなすことですが、2級ぐらいになるとプリント演習になかなか気が乗らない子が出てきます。
その場合は読上げ算を使うなどして、できるだけ楽しんで上達するようにしましょう!
段位の壁(モチベーション)
1級を合格し、段位になると最後の壁が出現します。
それがモチベーションになります。
初段、2段ぐらいまでは挑戦する気持ちが出るかもしれませんが、ある程度の段位まで行くと、どうしても限界を感じて楽しくなくなってきます。
これ以上どうやれば速く計算出来るんだよ…となってしまのです。
それに4段が5段になったところで…とも。
私自身そろばんを習うのを辞めてしまったのもこれが理由です。
こうなるとある種一つのゴールだと思い、辞めるのもいいと思います。
続ける場合は単に計算スピードを上げる事も必要ですが、こういう問題から解けば点数が上がるなど、改めてそろばんが楽しいと感じることが必要だと思います。
以上がそろばんを習い始めてから目の前に現れてくるそろばんの壁になります。
もし子供がそろばんに行くのに気分が乗らないのであれば、どんなことで悩んでいるのか相談に乗ってあげて下さい。
PC用広告
関連記事
-

-
そろばんの級と学年の目安はどのくらい?
どんな習い事でも同じ期間通っても、一人一人結果は異なります。もちろんそろばんに関しても同
-

-
そろばんは英語でabacus 海外でも注目!?
そろばんを英語でなんというかご存知ですか?記事のタイトルにも載せましたが、そろばんは英語で「abac
-

-
そろばんの問題が無料で手に入る!!
自分がそろばんを習っていた頃は小学生だったのと、まだまだインターネットがそこまで普及していなかった時
-

-
そろばんが上達しない理由【下級生編】
我が子をそろばん教室に通わせているのに、いっこうにそろばんが上達しないという気持ちを抱いている親御
-
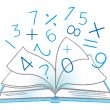
-
暗算ができるできないの差
そろばんを教えてるとそろばん(珠算)以上に生徒によって差がでるのが暗算です。 同じ学年の生徒で、珠
-

-
そろばんって何歳まで習うもの?
子供の習い事としてそろばんを選んだのだけど、「そろそろ辞め時かな、他の子はどのくらい続けているのだろ
-

-
そろばんではえんぴつとシャープペンのどちらを使うべきか
そろばんは計算をした後に答えの数字を紙に記入します。今回はそのときに「えんぴつとシャープペンのどちら
-

-
そろばんは左利きでも習えるの?
日本人の約11%が左利きといわれています。左利きというだけで羨ましいと思われることもあれば、当人は何
-

-
幼児向けそろばんテキストおすすめはこれ!【定番2種を徹底比較】
ここでは小学校就学前の幼児がそろばんを習うときに、おすすめするそろばんテキストをご紹介し